実印作成時に抑えるべき4つのポイント
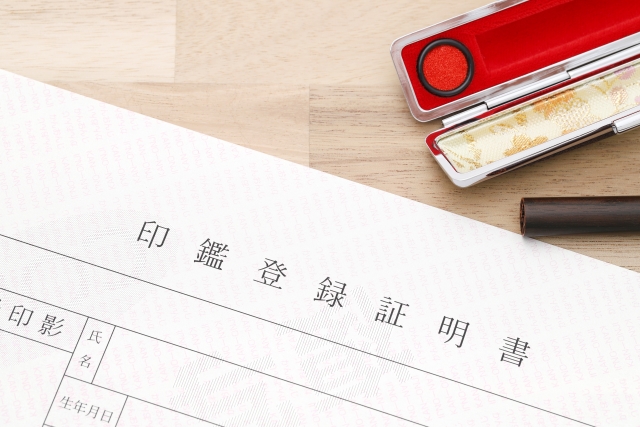
実印作成で失敗しない4つのポイント
実印は、不動産の取引や自動車の購入など、人生の重要な契約において、本人の意思を証明するための非常に大切な印鑑です。 一度作成すると長く使い続けるものだからこそ、後悔のないように選ぶ方法を知っておきましょう。
この記事では、実印作成において必ず押さえておくべき4つの重要なポイント(「素材」「大きさ」「書体」「管理方法」)を専門店の視点で分かりやすく解説します。 これらのポイントを知っておくことで、安心かつ、長く愛用できる実印を作成することができます。
1. 「素材」の選び方
実印は、ご自身の財産や権利を守るための重要な役割を担います。 長く扱うからこそこだわりたいのが、印鑑の基礎となる「素材」です。 選ぶ素材によって、耐久性はもちろん、捺印の鮮明さや見た目の風格が大きく変わります。
古くから愛されている定番の素材には、木のぬくもりがあり、細やかな彫刻にもぴったりな「柘植(つげ)」、重厚感としっとりとした黒光りが美しい「黒水牛」、そして一本一本異なる独特の模様が魅力の「オランダ水牛」などがあります。 これらはどれも、永く愛用できる十分な丈夫さを備えています。

さらに高い耐久性を大切にしたい方や、きらりと光る個性をお求めの方には、金属ならではの輝きと、欠けにくい強さが魅力の「チタン」も人気を集めています。

また、印材の王様と称される象牙と同様のクオリティを持つ「マンモス」は、きめ細かな材質が朱肉によく馴染み、美しい印影を残すことができる最高級の素材です。
それぞれの素材に長所がありますので、ご自身の価値観やご予算、そしてどのような場面で実印を使用するかを考慮して選ぶことが大切です。
幸宝堂でも、さまざまな素材の実印をご用意しておりますので、お気に入りの実印を見つけてみてください!
2. 「大きさ」の選び方
実印として役所に登録するためには、印影の大きさに規定があることをご存知でしょうか?
多くの市区町村では、「一辺の長さが8mmの正方形に収まらず、25mmの正方形に収まるもの」と定められています。 この規定から外れる大きさの印鑑は、実印として登録できないので注意が必要です。
この規定の範囲内で、一般的に推奨される大きさとして、男性の場合は、15.0mmから18.0mmが人気です。一方、女性の場合は、13.5mmから15.0mmが多く選ばれる傾向にあります。ただし、これはあくまで一般的な目安になりますので、サイズ選びの際には次のポイントを抑えましょう。
- 管理のしやすさ:
ご家族で実印を区別し、誤用を防ぐために、サイズを少し変えたり、異なる素材を選ぶことをおすすめします。 また、実印は銀行印や認印よりも大きめのサイズを選ぶと、用途の区別がつきやすく、管理がしやすくなるという利点があります。
- 文字のバランス:
お名前の文字数が多い方や、画数が多い方は、文字が潰れないように少し大きめのサイズを選ぶと、実印の持つ重厚感が際立ち、美しい印影を保つことができます。
実印はご自身の分身ともいえる存在です。規定を守りつつ、ご自身の名前のバランスや使いやすさを考慮して、最も納得のいく大きさをお選びください。
どのサイズが最適か迷われた際は、お気軽にご相談ください!
お問い合わせはこちら
3. 「書体」の選び方
実印の信頼性を保つために欠かせない要素のひとつが、「書体」です。 実印に用いられる書体は、第三者が容易に判読・模倣できないような複雑で可読性の低いものが推奨されます。
実印の書体として最も人気があり、推奨しているのは「篆書体(てんしょたい)」と「印相体(いんそうたい)」です。
- 篆書体(てんしょたい):
中国の古い時代に生まれた書体で、パスポートの表紙や公式の印章などにも多く使われています。 丸みがあり、左右対称に近い形が多く、上品で格式を感じさせるのが特徴です。普段見る文字とは形が異なるため読み取りにくいのですが、その「判読のしにくさ」こそがまねされにくく、実印として安心できる理由にもなっています。
- 印相体(いんそうたい):
印相体は篆書体をもとに、より複雑でデザイン性を高めた書体で、文字が枠にしっかり接しているため、印面が欠けにくく、偽造もされにくいという特長があります。
どちらも長く使う実印にふさわしい、落ち着きと信頼感のある書体です。
認印などでよく使われる「古印体(こいんたい)」や「隷書体(れいしょたい)」は、比較的読みやすいため、実印としての使用は避けるのが賢明です。

大切な財産を守るという実印の役割を最大限に果たすためにも、セキュリティ性の高い書体を選ぶことは非常に重要なポイントです。 書体による印影のイメージも確認しながら、最適なものを選びましょう。
4. 実印の「管理方法」
せっかく気に入った実印ができても、日々の扱いがおろそかでは台無しです。 普段から丁寧に保管しておくことで、必要なときにきちんと使用でき、思わぬトラブルや悪用のリスクも防ぐことができます。 印鑑を選ぶことと同じくらい、「どのように管理するか」を知っておくことが、安心して使い続けるためのポイントです。 実印を作るときは、ぜひ管理のことまで一緒に考えておきましょう。
まず、実印と呼ばれるためには、市区町村の役所で登録を行う必要があります。印鑑が完成したら、住民票のある市区町村役場で「印鑑登録」の手続きを行いましょう。 この手続きを経て、初めて法的な効力を持つ「実印」になります。
次に、保管する際は必ず「専用の印鑑ケース」に入れましょう。 印鑑を衝撃や傷から守るだけでなく、朱肉の油分による印材の劣化を防ぐ役割もあります。 また、盗難のリスクを避けるため、通帳や権利書といった重要書類とは別の場所に保管することが鉄則です。 金庫など、安全な場所に保管することを推奨します。

また、実印を使用した後は、朱肉をティッシュペーパーなどで優しく拭き取ってください。朱肉が残ったままだと、印面にゴミが溜まったり、印材が脆くなったりする原因になります。特に 木製や動物系素材(柘・黒檀・牛角など) の印鑑は、水分に弱いため、水洗いは避け、やわらかい布で乾拭きするのがおすすめです。一方で、チタン印鑑は水洗いが可能です。 汚れが気になるときは、水で軽くすすぎ、しっかり水気をふき取ってから保管してください。金属素材のため、印面が摩耗しにくく、お手入れしやすい点も大きなメリットです。
そして、万が一、紛失や盗難にあった場合は、直ちに警察へ届け出るとともに、役所で印鑑登録を廃止する手続きを行ってください。
上記のような正しい管理が、あなた自身を守ることにも繋がります。
まとめ
今回は、後悔しない実印を作成するために不可欠な「素材」「大きさ」「書体」「管理方法」という4つのポイントについて解説しました。
- 素材: 耐久性や見た目の好みなどを考慮し、ご自身の価値観に合ったものを選択。
- 大きさ: 役所の規定(8mm~25mm)を守りつつ、名前とのバランスや使いやすさで決める。
- 書体: 偽造防止のため、可読性が低く複雑な書体が選択。
- 管理方法: 印鑑登録を行い、印鑑ケースに入れて重要書類とは別の場所で厳重に保管。
実印は、あなたの人生における重要な節目において、あなた自身の証となる大切なパートナーです。これらのポイントをしっかりと押さえることで、安心して末永く使える、あなただけの一本となります。大切な節目に寄り添う印として、納得のいく一本をお選びください。










